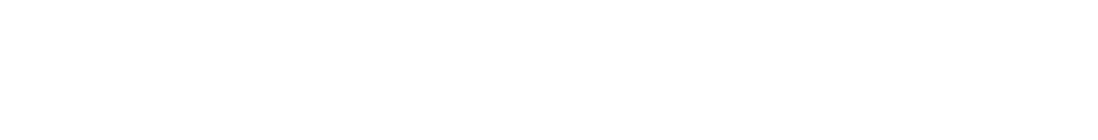- HOME>
- 骨盤臓器脱・性器脱
骨盤臓器脱・性器脱とは

骨盤臓器脱は、骨盤の底を支える筋肉や靭帯が弱くなることで、膀胱、子宮、直腸などの臓器が膣から下がってくる病気です。「下から何か出てくる感じがする」「股の間に何か挟まっている」といった不快な症状により、日常生活に支障をきたすことがあります。
出産経験のある女性に多く見られ、加齢とともに症状が現れやすくなります。恥ずかしさから受診をためらう方も多いですが、適切な治療により症状の改善が期待できる病気です。
このような症状があればご相談を
- 股の間に何か挟まっている感じがする
- 下から何か出てくる感覚がある
- 入浴時に膣に何か触れる
- 尿が出にくい、残尿感がある
- 長時間立っていると症状が悪化する
- 性交渉時の違和感
- など
骨盤臓器脱の種類
膀胱瘤(ぼうこうりゅう)
膀胱が膣の前壁から下がってくる状態です。最も多いタイプで、尿が出にくい、残尿感があるなどの排尿症状を伴うことがあります。
子宮脱
子宮が下がってきて、重症になると膣の外に出てしまうこともあります。下腹部の違和感や引っ張られる感じが特徴的です。
直腸瘤
直腸が膣の後壁から膨らんでくる状態です。排便困難や便が残る感じがすることがあります。
膣断端脱
子宮摘出手術を受けた方に起こることがある脱で、膣の上部が下がってくる状態です。
骨盤臓器脱・性器脱の原因
出産
経膣分娩により骨盤底筋群がダメージを受けることが最大の要因です。難産や多産、大きな赤ちゃんの出産などはリスクを高めます。
加齢
更年期以降、エストロゲンの減少により組織の弾力性が低下し、骨盤底を支える力が弱くなります。
慢性的な腹圧上昇
慢性的な咳、便秘、重い物を持つ仕事、肥満などにより、骨盤底に長期間圧力がかかることで発症しやすくなります。
体質的要因
生まれつき結合組織が弱い方は、骨盤臓器脱になりやすい傾向があります。ご家族に同じ症状の方がいる場合は注意が必要です。
骨盤臓器脱・性器脱の検査や診断
問診
いつから症状があるか、どのような時に症状が強くなるか、出産歴や手術歴などを詳しくお聞きします。日常生活への影響も重要な情報です。
内診
膣から臓器がどの程度下がっているかを確認します。いきんでもらったり、立った状態で診察したりすることもあります。
超音波検査(エコー検査)
残尿量を測定し、排尿障害の程度を評価します。また、臓器の下垂の程度もある程度確認できます。当院では主にこの方法で評価を行っています。
その他の検査
より詳しい評価が必要な場合は、専門機関で膀胱造影検査(チェーン膀胱造影)などの検査を受けていただくことがあります。
骨盤臓器脱が認められたら
重症度の評価
下垂の程度により、軽度から重度まで分類されます。症状の程度と必ずしも一致しないため、患者様の困り具合も含めて総合的に評価します。
合併症の確認
排尿障害や便秘など、骨盤臓器脱に伴う症状の有無を確認し、必要に応じて治療を行います。
骨盤臓器脱・性器脱の治療
骨盤底筋体操
軽度の場合は、骨盤底筋を鍛える体操が有効です。正しい方法で継続することが重要で、当院では分かりやすい指導を心がけています。専門的なトレーニングが必要な場合は、大阪中央病院のピラティス外来などと連携しています。
ペッサリー療法
膣内にリング状の器具を入れて、下がってきた臓器を支える治療法です。定期的な交換と管理が必要ですが、手術を希望されない方には良い選択肢となります。
手術療法
症状が重い場合や、保存的治療で改善しない場合は手術を検討します。メッシュを使った手術や、膣式手術など様々な方法があり、専門機関と連携して最適な治療法を選択します。
生活指導
便秘の改善、体重管理、重い物を持たない、慢性的な咳の治療など、腹圧を減らす生活習慣の改善も重要です。
当院での診療について

骨盤臓器脱は女性にとって非常にデリケートな問題で、誰にも相談できずに悩んでいる方が多い病気です。大阪市生野区のりょう泌尿器科内科クリニックでは、プライバシーに最大限配慮した診療環境で、安心して受診していただけるよう努めています。
エコー検査による評価を中心に、できるだけ患者様の負担が少ない方法で診断を行います。症状の程度により、骨盤底筋体操の指導から始め、必要に応じて専門機関と連携した治療を行います。
「年齢のせいだから仕方ない」と諦めている方も多いですが、適切な治療によりQOL(生活の質)は改善します。恥ずかしがらずに、まずはお気軽にご相談ください。